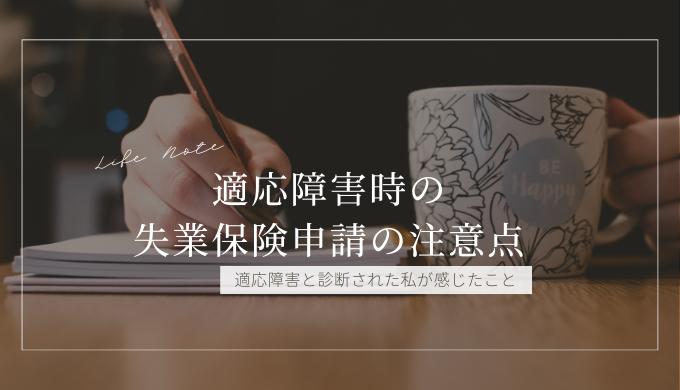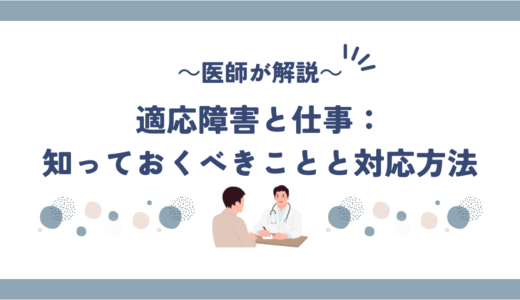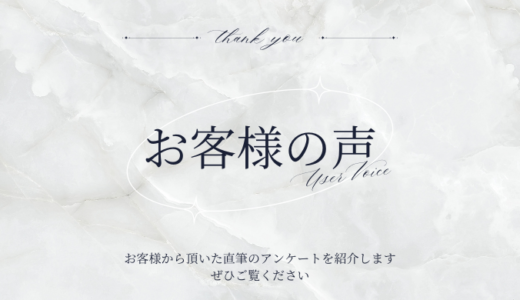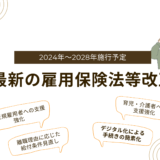適応障害が原因で退職した場合、失業保険を受給できるのか不安に感じる方は少なくありません。特に、精神的な負担を抱えながら複雑な手続きを進めなければならないため、申請に踏み出せずに悩むケースも多く見られます。
失業保険は、適切な手続きを踏めば、適応障害による退職後でも受給できる可能性があります。ただし、申請の際にはいくつか注意すべきポイントがあり、事前に知っておかないとスムーズに進まないこともあります。
本記事では、実際に私が適応障害で退職し、失業保険を申請した際に感じた注意点や基本的な知識について、解説しています。実際に適応障害と診断されている方や適応障害の疑いがある方などで失業保険の申請に不安を抱えている方の参考になれば幸いです。
1. 適応障害で失業保険は受け取れる?基本知識
適応障害を理由に退職した場合でも、一定の条件を満たしていれば失業保険(正式には「雇用保険の基本手当」)を受け取ることができます。ただし、受給にあたっては、いくつかの注意点や確認すべきポイントがあります。
まず、失業保険を受給するためには、退職前に雇用保険に一定期間加入していたことが条件となります。原則として、「離職前の2年間に通算して12か月以上、雇用保険に加入していたこと」が必要です。
また、失業保険の受給には「働く意思と能力があること」が求められます。適応障害による退職であっても、「すぐに就職できる状態」であると判断されなければ、失業保険の受給資格は得られません。もし医師から「就労不可」と診断されている場合は、受給が難しくなる可能性があるため注意が必要です。(なお、生命保険に加入している場合、就労不能金として保険金を受給できる可能性があるケースや、失業保険ではなく傷病手当金を受給できるケースがありますので、給付金受給サポートのプロにご相談するのがおすすめです。)
また、退職理由によって受給開始時期も異なります。自己都合退職の場合、原則として「待機期間7日間+給付制限期間2か月(※)」があり、その後に失業保険の支給が始まります。一方、会社都合退職の場合は給付制限期間がなく、より早く受給を開始できます。適応障害による退職が会社都合扱いとなるか自己都合扱いとなるかは、退職時の手続きや会社とのやりとりに左右されるため、離職票の記載内容は必ず確認しましょう。
(※)給付制限期間は、2025年4月以降「2か月」から「1か月」に短縮されています。
さらに詳しく「自己都合退職と会社都合退職の違い」について知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。
このように、適応障害で退職した場合でも失業保険の受給は可能ですが、事前に制度の仕組みを正しく理解しておくことが重要です。
2. 失業保険の手続きの際に経験したこと
適応障害を理由に退職した後、失業保険を申請する際には、通常の手続きに加えて注意すべき点がいくつかあります。ここでは、私が実際に失業保険を申請した際に経験した、退職から申請までに行ったことをまとめました。
まずは、全体の流れを把握するために、実際に取り組んだ主なステップを紹介します。
- 離職票など必要書類を早めに準備
- ハローワークで求職申込みと受給資格の確認
- 医師の診断内容を踏まえて就労可能と申告
- 自己都合・会社都合の扱いをハローワークで確認
- 支給開始までの期間を理解する
退職後、失業保険の申請に必要な「離職票(1・2)」や「本人確認書類」「マイナンバー確認書類」などを早めに揃えることが重要です。離職票の発行には時間がかかる場合もあるため、会社への催促を含め、早めの対応を心がけましょう。
ハローワークに足を運び、求職申込みを行うことで失業保険の受給資格が確認されます。この時点で、再就職への意欲や健康状態についても確認されるため、準備しておくとスムーズです。
適応障害で退職した場合でも、就労可能な状態であることを伝える必要があります。医師から「就労可能」と診断されている旨を説明できるようにしておくと、申請手続きが円滑に進みます。
退職理由によって失業保険の受給条件は大きく変わるため、自己都合退職か会社都合退職かをハローワークで必ず確認しましょう。会社からの説明と異なる扱いとなる場合もあるため、離職票の記載内容も要チェックです。
自己都合退職扱いとなった場合、7日間の待機期間に加え、1か月間の給付制限期間を経てから支給が始まります。この間の生活資金計画を立てておくことが、安心して申請手続きを進めるポイントになります。
私は、当記事を掲載しているMISVさんが実施しているLINEでの無料シミュレーションを活用し、どれくらい給付金が受給できるかを確認した上で、生活資金計画を立てたので、もしよければご活用ください!
このように、適応障害による退職後でも、しっかりと準備と手続きを進めることで、失業保険の受給は可能です。精神的な負担が大きい時期だからこそ、焦らず、確実に進めることが大切です。
3. 手続きで気を付けるべきポイント4選
適応障害で退職し、失業保険を申請する際には、通常の手続きだけでなく精神的・実務的に特有の注意点があります。ここでは、私が思う特に気をつけておきたい4つのポイントを紹介します。
失業保険を申請する際、ハローワークでは「現在、働ける状態かどうか」を確認されます。
適応障害の症状について、どこまで正直に伝えるべきか迷う方も多いですが、基本的には「働く意思と能力がある」という前提で申請する必要があります。
ただし、あまりに症状が重い場合や、医師から「休養が必要」と診断されている場合は、無理に就労可能と申告するのは避けるべきです。その場合は、失業保険ではなく「傷病手当」や「傷病手当金による受給延長制度」の対象となる可能性もあります。
申請時に医師の診断書の提出が求められるケースでは、診断書の記載内容に注意が必要です。
例えば、「○か月間の就労は困難」などの記載がある場合、ハローワークで「就労不可」と判断され、失業保険ではなく「受給期間延長」の手続きを案内されることもあります。
この場合、失業保険の受給は症状が改善してからとなり、すぐに受給できるわけではありません。診断書を提出する前に、主治医に「現時点での働く可能性」について相談しておくと安心です。
実際に現役の精神科医が適応障害の方に向けた記事もあるので、興味のある方はご参考ください。
適応障害で退職した場合、多くは自己都合退職扱いとなります。自己都合退職の場合、申請後すぐに失業保険が支給されるわけではなく、7日間の待機期間に加え、さらに1か月間の給付制限期間を経てから支給が開始されます。
この「1か月間の無収入期間」は精神的にも金銭的にも負担になるため、あらかじめ生活資金を確保しておく、家族や友人と相談して支援を得るなどの対策が必要です。
会社からの退職理由証明が不十分な場合でも、退職勧奨やパワハラによる退職などであれば、会社都合退職扱いになる可能性もあるため、ハローワークなどで詳細に相談しましょう。
失業保険を受給するには、定期的に「求職活動実績」を提出する必要があります。
具体的には、ハローワークのセミナー参加や求人応募など、一定の活動を行った証拠を提出しなければなりません。
しかし、適応障害の症状が残っている中で積極的な活動を行うのは、精神的に大きな負担になることもあります。無理に応募件数を増やそうとすると、かえって症状が悪化してしまうリスクもあるため、できるだけ負担の少ない方法(セミナー参加や職業相談)で実績を積み重ねることがポイントです。
このように、適応障害による退職後の失業保険手続きでは、単なる申請作業だけでなく、自分自身の体調や今後の生活設計を見据えた慎重な対応が求められます。焦らず、一つひとつ確実に対応していきましょう。
4. 失業保険以外に知っておきたい支援制度
適応障害で退職した場合、失業保険だけでなく、他にも利用できる支援制度があります。これらの支援制度を活用することで、生活の安定を図るとともに、再就職への準備を整えることができます。ここでは、失業保険以外で知っておきたい主要な支援制度をご紹介します。
傷病手当金は、病気やケガで働けない期間に、生活を支えるための給付金です。適応障害の場合も、症状が重く働けない場合には、傷病手当金を利用することができます。これは、健康保険に加入している期間中に支給されるため、退職後に継続して受け取ることはできませんが、退職前に支給を受けていた場合には、一定期間支給されることがあります。
傷病手当金は、給与の約3分の2程度が支給されるため、失業保険の給付を待つ間の収入源となり、精神的な負担を軽減する助けになる可能性もあります。
当社では、失業保険の受給サポートだけでなく、傷病手当金の受給サポートも行っております。退職後にいくら受給できるのかがわかる無料シミュレーションを当社公式LINEにて実施しておりますので、気になる方はぜひご活用ください。
失業保険や傷病手当金が受けられない、または受け取るまでに時間がかかる場合、生活保護を利用する選択肢もあります。生活保護は、収入がない、または収入が極端に少ない場合に、最低限の生活を保障するための制度です。
生活保護は、都道府県の福祉事務所で申請することができ、受給基準は世帯の収入や資産などを基に決定されます。適応障害により就労が困難な場合でも、収入がない状況が続けば支給される可能性があります。
職業訓練受講給付金は、再就職を目指して必要なスキルや知識を学ぶために支給される金銭的支援です。適応障害から回復し、再就職を目指す際に役立つスキルアップを支援するための制度として活用できます。
ハローワークが提供する職業訓練に参加することで、一定の条件(月収が8万円以下であることや失業保険を受給していないこと等)を満たせば、毎月10万円の支援金(2025年5月現在)を受給することが可能です。受講に関する規則や受給条件などが細かく設けられており、制度は細かに見直される可能性があるので、最新の情報はぜひ厚生労働省のHPでチェックするのが良いでしょう。
就職活動をする際に、専門のキャリアカウンセリングを無料で受けることができます。特に精神的な障害を抱える方にとって、就職活動は精神的な負担が大きくなりがちですが、専門家によるカウンセリングを受けることで、適切なアドバイスや支援を受けることが可能です。
当社でもキャリア形成に関する相談も受け付けてはおりますが、失業保険の受給サポートがメインとなりますので、今後のキャリアについて不安な方は、以下のようなキャリアカウンセリングサービスを活用してみてください。
参考:キャリアコンサルティング(厚生労働省委託事業 キャリア形成リスキリング 相談コーナー)
このように、失業保険以外にも適応障害で退職した場合には、さまざまな支援制度を活用することができます。これらの支援制度をうまく利用することで、精神的な負担を軽減し、再就職に向けての準備を整えることが可能です。自分に合った支援を受けることで、回復への道のりをサポートすることができるので、ぜひ活用を検討してみてください。
まとめ
本記事では、当社でご支援している適応障害罹患者が実際に失業保険を受給した際の声を交えて失業保険について解説いたしました。その他、当社にてご支援している方の声を実際の直筆アンケートにまとめて記載しましたので、ぜひご覧ください。